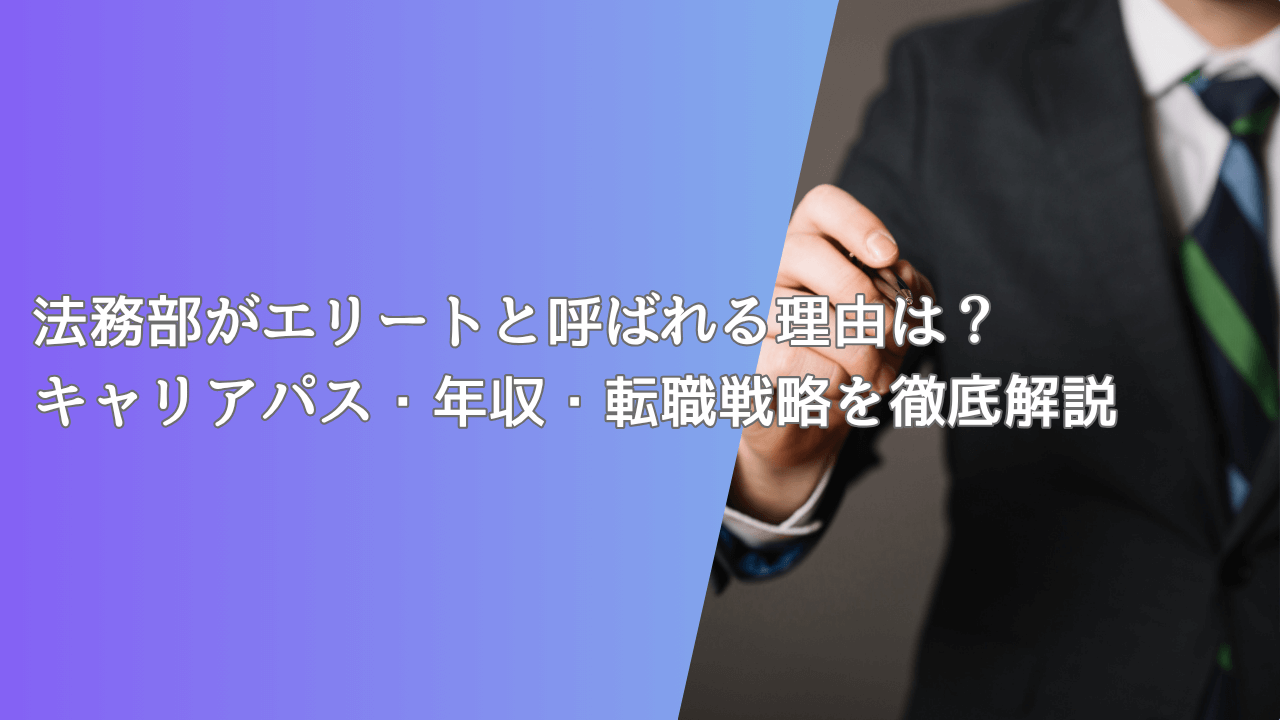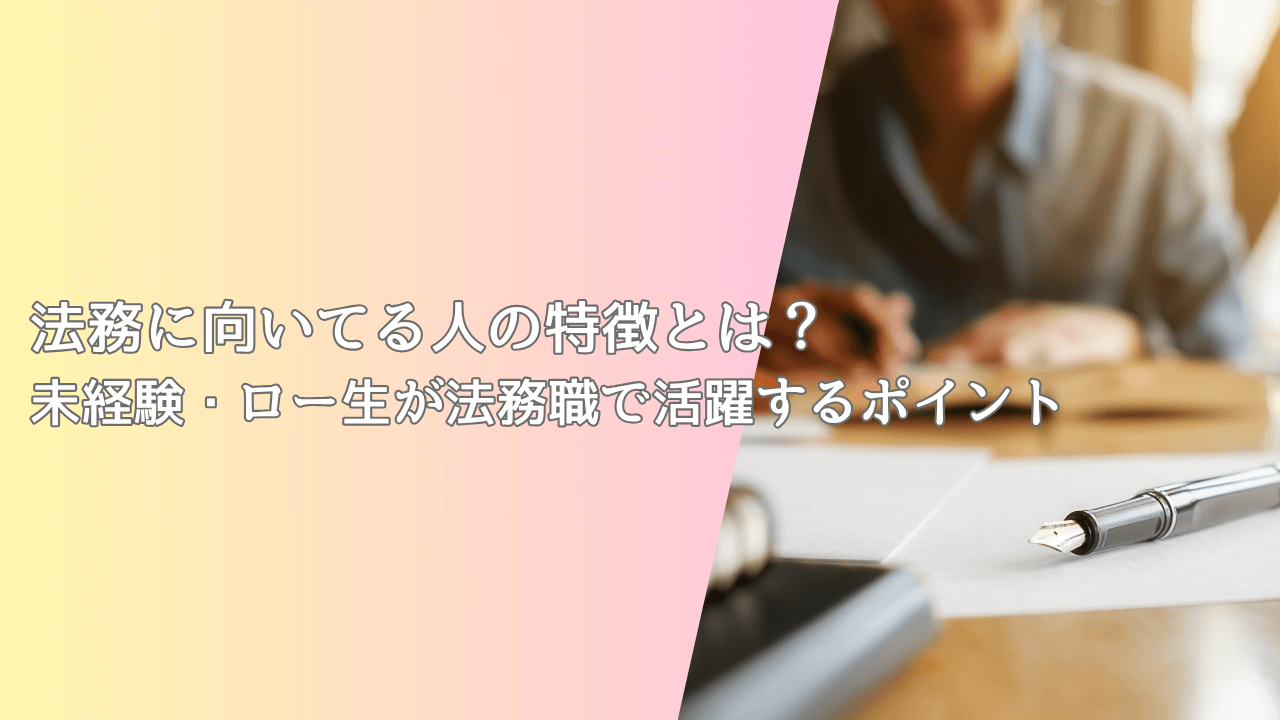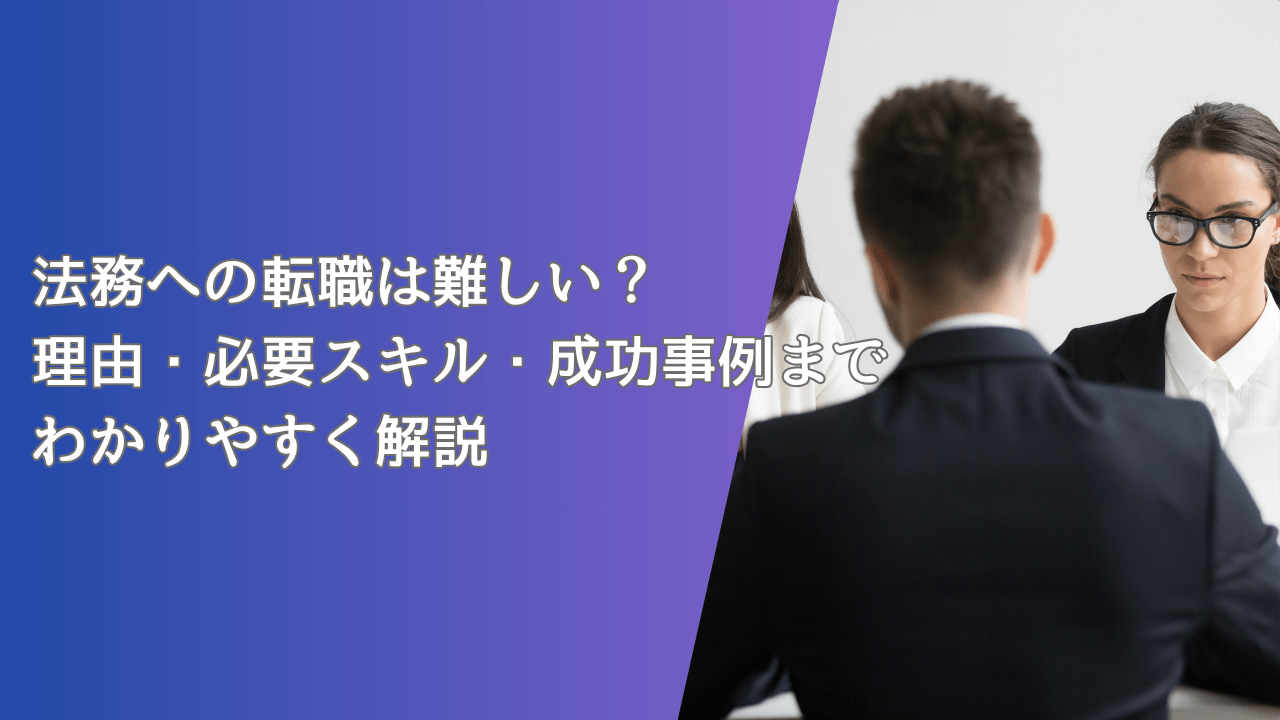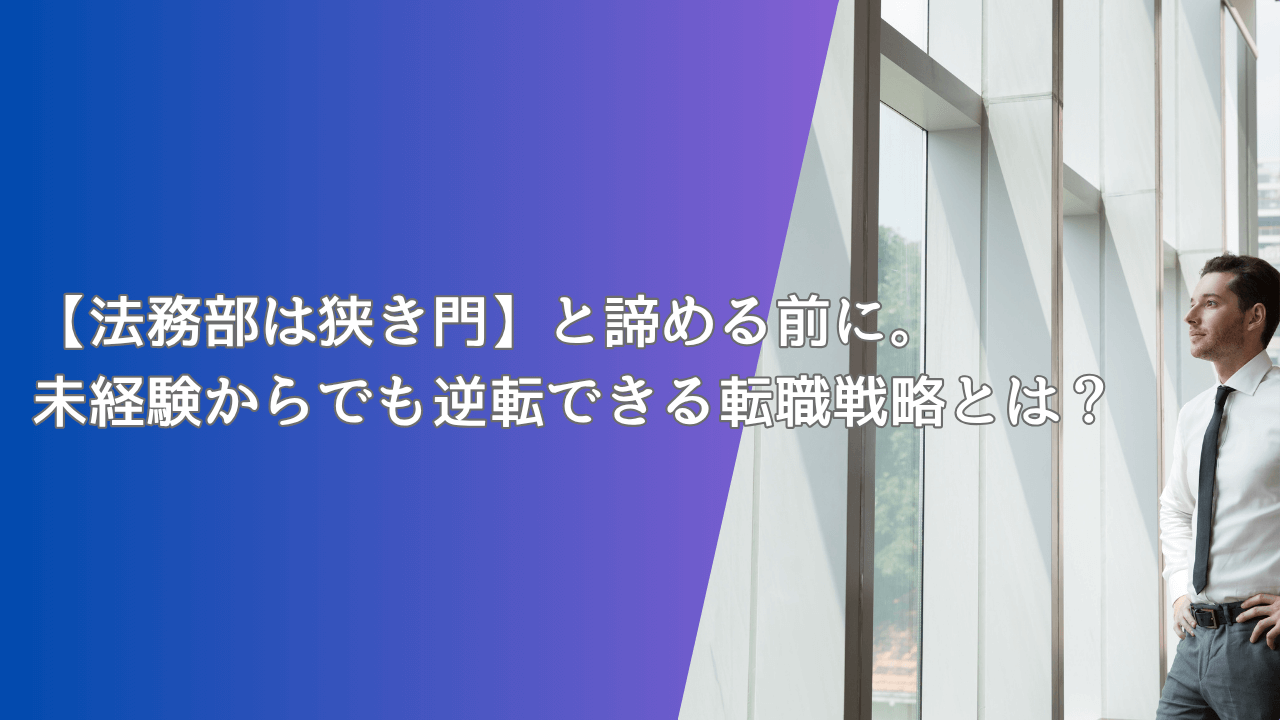法務の仕事内容とは?未経験・兼務でもわかる役割から契約レビュー、年収まで徹底解説
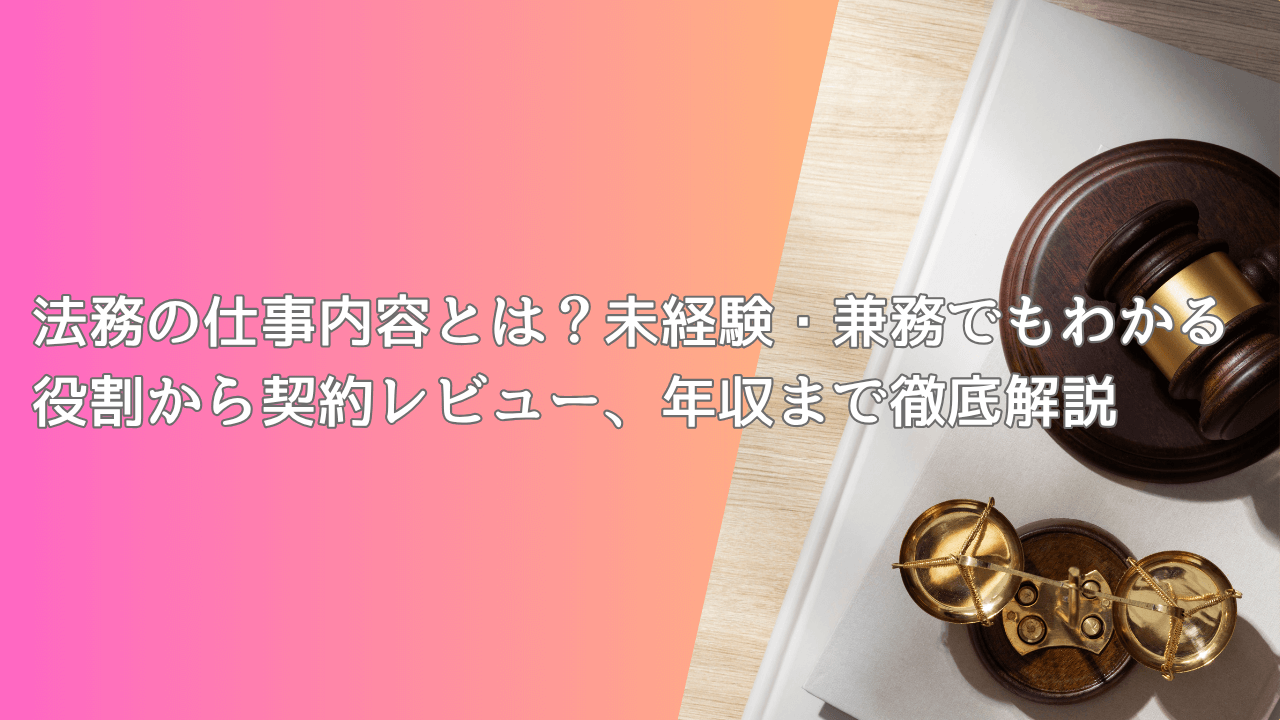
「急に上司から『来月から法務も兼務で頼む』と言われたけれど、一体何から手をつければいいんだろう…」
「初めて見る契約書を前に、どこからチェックすればいいのか全く分からない…」
総務や人事など他の業務と兼務しながら、初めて法務の仕事に携わることになったあなたは、今まさにこのような不安や戸惑いの真っ只中にいるのではないでしょうか。
専門用語が並ぶ契約書、範囲が広く全体像が見えにくい業務内容。法務という仕事は専門性が高いイメージがあるからこそ、何から学べばいいのか途方に暮れてしまいますよね。
ご安心ください。この記事は、そんなあなたのための「最初の教科書」として、法務の仕事の全体像から実務で役立つ具体的なノウハウまでを、どこよりも分かりやすく解説するために作られました。
この記事を読み終える頃には、
- 法務の仕事の全体像という「地図」が手に入り、自分の役割が明確になる
- 契約書レビューで「どこを・なぜ見るべきか」が分かり、自信を持って取り組めるようになる
- 未経験からでも描けるキャリアパスと、年収のリアルな見通しが立つ
など、漠然としていた不安が「明日から何をすべきか」という具体的な行動計画に変わっているはずです。
10年以上にわたり、東海地区で多くの法務未経験者のキャリアを支援してきた専門家が、あなたの新たな一歩を力強くサポートします。さあ、一緒に法務という仕事の地図を広げ、あなたのキャリアの可能性を拓いていきましょう。
まずはここから!法務の仕事内容の全体像を理解しよう
「急に上司から『来月から法務も兼務で頼む』と言われたけれど、一体何から手をつければいいんだろう…」
「契約書をチェックしてと言われたけど、どこを見ればいいのか全くわからない…」

総務や人事など、他の業務と兼務しながら初めて法務に携わる方にとって、このような悩みはごく自然なことです。法務の仕事内容は多岐にわたるため、全体像が見えずに戸惑ってしまうことも少なくありません。

まずは、法務という仕事の「地図」を手に入れるところから始めましょう。全体像を理解することで、一つひとつの業務が会社のどの部分を守り、支えているのかが明確になります。
法務の役割は3つのステージ(予防・臨床・戦略)でわかる
法務の仕事内容は、その目的によって大きく3つのステージに分類できます。それは、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」、発生してしまったトラブルに対応する「臨床法務」、そして事業の成長を法的な側面から後押しする「戦略法務」です。

その通りです。それぞれのステージを理解することで、ご自身の業務がどの役割を担っているのかを意識できるようになります。特に未経験や兼務で始める方は、まず「予防法務」が中心的な役割となることが多いです。
| 法務のステージ | 主な役割と目的 |
|---|---|
| 予防法務 | 契約書のレビューや社内規程の整備を通じて、法的なトラブルが発生するのを未然に防ぐ(守りの要) |
| 臨床法務 | 実際に発生した顧客とのトラブルや訴訟などに対応し、会社の損害を最小限に抑える(事後対応) |
| 戦略法務 | M&Aや新規事業の立ち上げ、知的財産の活用など、法的な視点から経営戦略をサポートし、企業価値向上に貢献する(攻めの法務) |
これらのステージは独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。例えば、しっかりとした予防法務が機能していれば、臨床法務の出番を減らすことができます。まずは、日々の業務が将来のトラブルを防ぐための重要な「予防」活動なのだと意識することから始めてみましょう。
【未経験・兼務向け】法務の仕事内容一覧
3つのステージを理解したところで、次に未経験や兼務の担当者が担当することが多い、具体的な法務の仕事内容を見ていきましょう。最初からすべてを完璧にこなす必要はありません。まずは基本的な業務から一つずつ着実に身につけていくことが大切です。

主に、以下の業務からスタートすることが一般的です。
- 契約書のレビュー・作成・管理:取引先と交わす秘密保持契約(NDA)や業務委託契約書などの内容を確認し、自社に不利な条項がないかチェックします。ひな形(テンプレート)の管理も重要な仕事です。
- 社内規程の作成・改訂:就業規則や個人情報保護規程など、会社のルールブックを法改正や実情に合わせて見直します。
- コンプライアンスに関する教育・啓発:全従業員が法律や社内ルールを守って行動できるよう、研修を企画したり、注意喚起の情報を発信したりします。
- 社内からの法律相談への一次対応:「この取引、法律的に問題ない?」「この表現は許される?」といった他部署からの相談窓口となります。
- 商業登記関連業務:役員変更や本店移転などがあった際に、法務局へ提出する書類の準備をサポートします。
これらの業務は、会社を法的なリスクから守るための土台となる、非常に重要な仕事内容です。
どこまでが自社の仕事?弁護士に相談すべき境界線
法務の仕事を進める上で、必ず直面するのが「この判断は自分でしていいのか、それとも専門家である弁護士に相談すべきか」という悩みです。この境界線を誤ると、会社を大きなリスクに晒してしまう可能性もあります。

その不安、とてもよくわかります。重要なのは、「迷ったら相談する」という原則を持つことです。特に、弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を行うことを原則として禁止しています(非弁行為)。社内法務としての業務はこれに該当しませんが、安易な法的判断は禁物です。
| 社内対応が中心の業務例 | 弁護士への相談を検討すべき業務例 |
|---|---|
| ひな形に沿った契約書の軽微な修正 | 訴訟や紛争に発展している、またはその可能性が高い案件 |
| 社内規程の定期的な見直し | M&A、事業譲渡など、高度な専門知識を要する案件 |
| 社内からの簡単な法律相談への一次回答 | 相手方から前例のない特殊な契約条件を提示された場合 |
社内法務の重要な役割の一つは、社内で発生した法的課題を整理し、弁護士がスムーズに判断できるための「橋渡し」をすることです。事実関係を正確にまとめ、何に困っていて、何を判断してほしいのかを明確にしてから相談することで、的確なアドバイスを得られ、結果的にコストの削減にも繋がります。
顧問弁護士がいる場合は、気軽に相談できる関係性を普段から築いておくことが、いざという時に会社を守る防波堤となります。
※この記事は法務に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的アドバイスを行うものではありません。具体的な法律問題については、必ず弁護士にご相談ください。
【最重要】契約法務の仕事内容と具体的な進め方
法務の仕事内容の中でも、未経験の方が最初に任されることの多い業務が「契約法務」です。これは、企業活動のあらゆる場面で交わされる「契約書」の作成やレビュー(内容の確認)、管理を行う仕事です。

その気持ち、非常によくわかります。しかし、契約法務は会社の利益を守り、未来のリスクを回避する「予防法務」の要です。一つひとつの契約書に丁寧に向き合うことが、事業を安定させるための第一歩となります。ここからは、契約法務の具体的な進め方について、わかりやすく解説していきます。
契約書レビューで見るべき基本チェックリスト【テンプレート付】
契約書レビューと聞くと難しく感じるかもしれませんが、実は確認すべきポイントはある程度決まっています。毎回ゼロから考えるのではなく、基本となる「チェックリスト」に沿って確認することで、抜け漏れを防ぎ、レビューの質を安定させることができます。

まずは、以下の基本的なチェックリストを参考に、レビューの型を身につけましょう。
| チェック項目 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 契約当事者 | 契約を結ぶ会社名、代表者名、住所は正確か?(登記情報と一致しているか) |
| 契約の目的・業務内容 | 「何をするための契約か」が明確に書かれているか? 委託する業務の範囲は適切か? |
| 契約期間 | いつからいつまでの契約か? 自動更新の有無やその条件は自社に不利ではないか? |
| 契約金額・支払条件 | 金額、支払時期、支払方法は明確か? 消費税の扱いはどうなっているか? |
| 秘密保持義務 | 秘密情報の定義や範囲は適切か? 義務を負う期間はいつまでか? |
| 損害賠償 | 賠償責任を負う範囲や上限額は、一方的に不利な内容になっていないか? |
| 契約解除 | どのような場合に契約を解除できるか? 自社にとって不当に厳しい条件はないか? |
| 管轄裁判所 | 万が一、裁判になった場合、どこの裁判所で争うことになるか?(自社から遠すぎないか) |
※これはあくまで一般的なサンプルです。実際に運用する際は、各社の実情に合わせて弁護士等の専門家と相談の上、カスタマイズしてください。
テンプレート活用で効率化!契約業務のフロー例
契約業務を効率的に、かつミスなく進めるためには、業務フローを標準化することが非常に重要です。依頼方法がバラバラだったり、レビューの進め方が属人化していたりすると、無駄な手戻りやミスの原因になります。

そこで有効なのが、契約書テンプレートの整備と、レビューフローの可視化です。例えば、東海地区のあるA社では、NDA(秘密保持契約)のテンプレートとレビューフローを整備したことで、1件あたりのレビュー時間を約30%削減できたという事例もあります。
以下に、基本的な契約業務のフロー例をご紹介します。
- 事業部門からの依頼:事業部門が、取引の概要や懸念点を専用の依頼フォームに記入し、法務担当へレビューを依頼します。
- 法務担当の一次レビュー:法務担当は、前述のチェックリストを用いて契約書案を確認し、リスクを洗い出します。
- 修正案の作成とすり合わせ:リスク箇所について修正案を作成し、その意図を事業部門へ説明・共有します。
- エスカレーション(必要な場合):判断に迷う論点やリスクが高い案件は、上長や顧問弁護士に相談します。
- 相手方との交渉:事業部門が主体となり、法務担当のサポートのもとで相手方と条件交渉を行います。
- 合意・締結:双方が合意したら、契約書を締結します。電子契約サービスを利用するのも有効です。
- 契約書管理:締結した契約書は、管理台帳に登録し、いつでも検索・閲覧できるように保管します。
この流れを社内で共有するだけでも、各部署の役割が明確になり、業務がスムーズに進むようになります。
「この条文は危険?」未経験者が知るべきリスク判断のポイント
契約書レビューに慣れないうちは、どの条文が「危険」なのか判断に迷うことが多いでしょう。中には、気づかないうちに自社が一方的に重い責任を負わされたり、将来の事業展開を縛られたりするような「危険な条文」が潜んでいることがあります。

以下のような条文を見つけたら、すぐにサインせず、一度立ち止まってその意味を慎重に検討するか、上長や専門家に相談するようにしてください。
| 危険な条文のパターン | なぜ危険なのか? |
|---|---|
| 損害賠償の範囲が「一切の損害」となっている | 予期せぬ間接的な損害(逸失利益など)まで、無限に賠償責任を負うリスクがあります。賠償額に上限を設けるか、「直接かつ通常の損害」に限定する交渉を検討すべきです。 |
| 自社の義務は「甲は〜しなければならない」と断定的なのに、相手方の義務は「乙は〜するよう努めるものとする」と努力義務になっている | 自社だけが重い義務を負い、相手方の責任は曖昧になる「片務的」な契約である可能性があります。双方の義務が公平になるよう修正を求めましょう。 |
| 成果物の知的財産権が、すべて相手方に帰属するとされている | 自社が開発した技術やノウハウを、今後自由に活用できなくなる恐れがあります。権利の帰属については、慎重に交渉する必要があります。 |
| 相手方からはいつでも自由に契約解除できるのに、自社からは解除できない、または非常に厳しい条件が課されている | 事業環境の変化に対応できず、不利な契約に長期間縛られてしまうリスクがあります。公平な解除条件を設定することが重要です。 |
これらのポイントは、契約法務の仕事内容のほんの一部ですが、非常に重要な観点です。もし少しでも「おかしいな?」と感じたら、それはあなたの法務担当者としての重要なセンサーが働いている証拠です。その感覚を大切にし、必ず確認する癖をつけましょう。
会社を守るコンプライアンス・機関法務の仕事内容
契約法務が取引先との「個別の約束」を守る仕事だとすれば、これからお話しするコンプライアンスや機関法務は、「会社組織そのもの」を守り、社会的な信頼を築くための仕事です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、会社の土台を固める非常にやりがいのある仕事内容です。

コンプライアンスとは、単に「法令遵守」と訳されるだけでなく、企業倫理や社会規範など、より広いルールを守ることを意味します。この体制を整えることが、企業の持続的な成長と信頼獲得に不可欠です。
コンプライアンスで取り組むべき社内規程の整備と周知
コンプライアンス体制構築の第一歩は、会社の公式なルールブックである「社内規程」を整備し、それを全従業員に「周知」することです。ルールブックがあっても、本棚の飾りになっていては意味がありません。

例えば、近年特に重要視されているハラスメント防止。東海地区のあるB社では、法改正に合わせてハラスメント防止規程を整備し、全社研修を実施したことで、「相談しやすい環境ができた」と従業員の安心感醸成に繋がったという実例があります。
まずは、自社に最低限必要な規程が揃っているか確認するところから始めましょう。
| 整備すべき主要な規程の例 | 主な目的と関連法規 |
|---|---|
| 就業規則 | 労働時間や賃金など、労働条件の基本ルールを定める(労働基準法) |
| 個人情報保護規程 | お客様や従業員の個人情報の適切な取り扱い方法を定める(個人情報保護法) |
| ハラスメント防止規程 | パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの防止策や相談窓口を定める(労働施策総合推進法など) |
| 情報セキュリティ規程 | 会社の機密情報やIT資産をサイバー攻撃などの脅威から守るためのルールを定める |
これらの規程を整備したら、入社時研修や定期的な勉強会などを通じて、従業員一人ひとりにその重要性を伝えていくことが法務担当者の大切な役割です。
機関法務の基本(取締役会・株主総会の運営サポート)
機関法務とは、株式会社の運営に不可欠な意思決定機関である「株主総会」や「取締役会」が、法律(主に会社法)に則って正しく運営されるようサポートする仕事です。

例えば、取締役会の招集通知に不備があった場合、その取締役会で行われた決議が後から「無効」だと主張されるリスクがあります。そうした事態を防ぎ、会社の重要な意思決定を法的に有効なものにするのが、機関法務の重要な仕事内容です。
- 取締役会の運営サポート:開催スケジュールの管理、招集通知の発送、議題の整理、そして最も重要な「議事録」の作成・保管を行います。議事録は、会社の意思決定を証明する法的な証拠となります。
- 株主総会の運営サポート:年に一度の最も重要なイベントです。招集通知や事業報告などの書類作成、当日のシナリオや想定問答集の準備、総会後の登記手続きまで、その業務は多岐にわたります。
これらの業務は、会社という組織の根幹を支える、まさに「縁の下の力持ち」と言えるでしょう。
上場準備で特に重要になる法務の仕事内容とは
もし、あなたの会社が将来的に株式上場(IPO)を目指している場合、法務の仕事の重要性は格段に高まります。なぜなら、証券取引所から「投資家が安心して投資できる、管理体制の整った会社である」と認められる必要があるからです。

上場準備段階では、これまでの法務業務に加えて、以下のような専門的な仕事内容が求められるようになります。
- 内部統制システムの構築:会社の業務が法令や社内規程に従って適正に行われるための仕組みを構築・運用します。
- 関連当事者取引の管理:社長や役員とその親族など、会社と特別な関係にある人々との取引が、会社に不利益を与えていないかを厳しくチェックします。
- 反社会的勢力との関係遮断:取引先に反社会的勢力がいないかをチェックする体制を構築します。
- 各種規程の全面的な見直し:上場企業として求められる水準にまで、すべての社内規程をブラッシュアップします。
私たち株式会社クルーは、社外CFOサービスやIPO支援も手掛けており、特に東海地区で上場を目指す多くの企業様をご支援してきました。その経験から言えるのは、上場準備は一朝一夕にはできないということです。将来を見据え、早い段階から管理体制を整えていくことが、スムーズな上場への鍵となります。
法務の仕事内容で求められるスキルと有利になる資格
ここまで法務の具体的な仕事内容を見てきましたが、「やっぱり法律の専門家じゃないと難しそう…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。もちろん法律知識は重要ですが、それだけで法務の仕事が務まるわけではありません。

ご安心ください。実務の現場では、法律知識と同じくらい、あるいはそれ以上に大切なスキルがあります。特に未経験や兼務からスタートする場合、今お持ちのビジネススキルを活かせる場面がたくさんあります。
法律知識だけじゃない?現場で本当に役立つスキルとは
法務は、ただ法律の条文を当てはめるだけの仕事ではありません。事業部門の「やりたいこと」を理解し、法的なリスクを分析した上で、どうすれば安全に実現できるかを一緒に考える「ビジネスパートナー」としての側面が非常に重要です。

法務の仕事内容で特に役立つのは、以下のようなポータブルスキル(持ち運び可能な能力)です。
| 現場で役立つスキル | なぜ重要なのか? |
|---|---|
| コミュニケーション能力 | 事業部門から相談の背景を正確に聞き出したり、難しい法律の話を分かりやすく説明したりするために不可欠です。 |
| 調査・情報収集能力 | 法改正や新しい判例をキャッチアップし、自社への影響を迅速に調査する力。未知の課題に直面した際の対応力が問われます。 |
| 論理的思考力 | 複雑なトラブルの事実関係を整理し、法的な観点から筋道を立てて解決策を導き出すために必要です。 |
| ビジネスへの理解力 | 自社の事業や業界の慣習を理解することで、単に「No」と言うだけでなく、事業を止めない代替案を提案できます。 |
これらのスキルは、総務や人事、営業など、他の職種で培った経験の中で十分に身につけられるものです。ご自身の経験を振り返り、法務の仕事に活かせそうなスキルをぜひ見つけてみてください。
未経験から法務を目指すなら?おすすめの資格と勉強法
「自分のスキルを客観的に証明したい」「何から勉強すればいいかわからない」という方にとって、資格の取得は有効な手段の一つです。資格がなければ法務になれないわけではありませんが、知識レベルの証明や、学習のペースメーカーとして役立ちます。

未経験から法務を目指すのであれば、まずは「ビジネス実務法務検定試験®」の3級または2級から挑戦することをおすすめします。この資格は、特定の業種に偏らない、ビジネス全般で求められる法律知識を体系的に学べるため、実務に直結しやすいのが特徴です。
- 勉強法①:市販のテキストや問題集を活用する
まずは検定試験の公式テキストなどを一冊読み通し、全体像を掴むことから始めましょう。 - 勉強法②:契約書のサンプルを読んでみる
書籍やウェブサイトで公開されている契約書のサンプルに目を通し、「どんなことが書かれているのか」に慣れるのも効果的です。 - 勉強法③:官公庁のサイトをチェックする
消費者庁や公正取引委員会などのウェブサイトには、企業活動に関わる重要な情報が掲載されています。定期的にチェックする習慣をつけることで、法改正への感度が高まります。
独学に不安を感じる場合は、私たちのようなキャリアの専門家に相談するのも一つの方法です。あなたのキャリアプランに合った学習計画を一緒に考えることができます。
ビジネス実務法務検定は意味ない?判断基準・実務活用・転職のリアル
法務資格の種類・難易度・選び方を徹底解説【キャリアアップに役立つ資格とは?】
職務経歴書でアピールすべき経験と効果的な書き方
「法務は未経験だから、職務経歴書に書けることがない…」と思っていませんか?そんなことはありません。先ほどお話ししたように、これまでの経験の中に必ず法務に活かせる要素は隠れています。大切なのは、その経験を「法務の視点」で光を当ててあげることです。

| 現在の職種 | 法務としてアピールできる経験の例 |
|---|---|
| 総務 | ・社内規程の改訂・管理 ・備品購入や業者選定時の契約内容の確認 ・株主総会の運営サポート |
| 人事 | ・雇用契約書の作成・管理 ・就業規則の改訂 ・プライバシーマーク取得に関する業務 |
| 営業・購買 | ・顧客や取引先との契約交渉 ・取引基本契約書やNDAの締結経験 ・見積書や発注書の条件確認 |
職務経歴書に書く際は、単に「〇〇をしました」と書くだけでなく、「(課題や状況に対して)どのような工夫や行動をし、その結果どうなったか」を具体的に記述することが重要です。
例えば、「契約書テンプレートを導入し、レビューフローを標準化したことで、月間のレビュー時間を10時間削減し、事業部門のスピード向上に貢献しました」のように、具体的な行動と成果をセットで示すことで、採用担当者へのアピール力は格段に高まります。
私自身、求職者の方のカウンセリングから企業へのヒアリングまで一貫して担当しているため、「企業が職務経歴書のどこに注目し、どんな経験を評価するのか」を熟知しています。あなたの経験を最大限に活かすための職務経歴書の書き方も、具体的にアドバイスさせていただきます。
法務のキャリアと年収のリアル
ここまで法務の具体的な仕事内容や必要なスキルについてお話ししてきましたが、皆さんが次に気になるのは、「この仕事に将来性はあるのか?」「実際、どれくらい稼げるようになるのか?」といったキャリアや年収のリアルな部分ではないでしょうか。

その気持ち、とても大切です。自分のキャリアプランを描く上で、やりがいだけでなく、将来性や待遇面をしっかりと見据えることは不可欠です。ここからは、法務という仕事のキャリアパスと、気になる年収の現実について、データを交えながら詳しく見ていきましょう。
法務の仕事内容における「やりがい」と「向いている人」の特徴
法務の仕事は、時に地道で細かな作業の連続ですが、それを上回る大きなやりがいがあります。また、法務の仕事内容には特有の適性があり、「向いている人」には共通した特徴が見られます。

| 法務の仕事の「やりがい」 | 法務の仕事に「向いている人」 |
|---|---|
| 専門性が直接会社の利益に繋がる 自身の法律知識や交渉力が、不利な契約を防ぎ、会社の損失を未然に防いだ時に大きな達成感を得られます。 |
知的好奇心が旺盛で、学び続けられる人 法改正や新しい判例など、常に知識をアップデートしていくことが求められるため、学ぶことが好きな人に向いています。 |
| 経営層のパートナーとして意思決定に関われる 新規事業やM&Aなどの重要な経営判断に、法的な観点から関与できる機会が多くあります。 |
物事を論理的に考え、整理するのが得意な人 複雑な事象を冷静に分析し、問題点やリスクを筋道立てて説明する能力が活かされます。 |
| 「会社の守護神」として頼られる存在になれる 他部署から「困った時の頼れる相談相手」として信頼され、感謝される場面が多くあります。 |
誠実で、正義感が強い人 ルールを守り、公正な判断を下すことにやりがいを感じる、真面目で誠実な人柄が信頼に繋がります。 |
もし、これらの特徴に一つでも当てはまるなら、あなたは法務担当者としての素質を十分に秘めていると言えるでしょう。
法務に向いている人の特徴とは?未経験・ロー生が法務職で活躍するポイント
【データで見る】法務の平均年収とキャリアパス
専門職である法務は、経験を積むことで年収アップも期待できる職種です。厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、企業法務担当の全国平均年収は約481.4万円とされています。

年齢階級別に見ると、経験と共に年収が上昇していく傾向がはっきりとわかります。
| 年齢 | 平均年収 |
|---|---|
| 20~24歳 | 310.52万円 |
| 25~29歳 | 390.59万円 |
| 30~34歳 | 444.59万円 |
| 35~39歳 | 476.35万円 |
| 40~44歳 | 500.53万円 |
出典:厚生労働省「職業情報提供サイト(job tag)」企業法務担当https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/446
もちろん、これは全国平均であり、企業規模や業界、個人のスキルによって変動します。そして、法務としてのキャリアパスは一つではありません。大きく分けて、以下のような道筋が考えられます。
- 法務スペシャリスト:契約、知的財産、M&Aなど、特定の分野の専門性を徹底的に磨き、その道の第一人者を目指すキャリア。
- 管理部門のジェネラリスト:法務を軸に、人事、総務、経理など管理部門全体を統括するマネージャーや本部長、将来的にはCLO(最高法務責任者)を目指すキャリア。
- 事業部門へのキャリアチェンジ:法務で培ったリスク管理能力やビジネス理解を活かし、経営企画や事業開発といった、より事業に近いポジションへ挑戦するキャリア。
東海地区の法務転職市場のリアルと弊社のサポート実績
私、後藤は10年以上にわたり、一貫して東海地区の管理部門・士業分野の転職支援に携わってきました。その経験からお話しすると、東海地区では、特に成長意欲の高い製造業やIT企業を中心に、法務人材の需要が年々高まっていると実感しています。

しかし、こうした優良な未経験者向け求人は、応募が殺到するのを避けるために一般には公開されず、「非公開求人」として私たちのような転職エージェントにのみ寄せられるケースがほとんどです。
私たち株式会社クルーの強みは、以下の3点に集約されます。
- 未経験者の可能性を引き出すカウンセリング:私たちは、あなたのこれまでの経験を丁寧に棚卸しし、法務の仕事に活かせる強みを見つけ出し、企業に効果的にアピールする方法を一緒に考えます。
- 東海地区での豊富なネットワーク:長年培ってきた地域企業との深い信頼関係により、他では見つからない独自の求人情報や、求人票だけではわからないリアルな社風までお伝えできます。
- ミスマッチを防ぐ「一気通貫」のサポート:私が直接、求職者様と企業様の両方からお話を伺うため、入社後の「こんなはずじゃなかった」というギャップを最小限に抑える、精度の高いマッチングが可能です。
法務としてのキャリアに少しでも興味が湧いたら、まずは情報収集から始めてみませんか?あなたの可能性を最大限に引き出すお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽に、あなたのキャリアプランをお聞かせください
この記事を読んで、法務の仕事内容やキャリアに少しでも興味が湧いたなら、ぜひ一度お話をお聞かせください。「今すぐ転職したい」という方でなくても、全く問題ありません。

初回のご相談は無料です。お一人おひとりのお話をじっくりとお聞きし、無理に転職をお勧めすることは決してありません。あなたのこれからのキャリアにとって、何が最善の道なのかを一緒に見つけていきましょう。
どんな小さな悩みでも、まずはお気軽にご相談ください。ご連絡を心よりお待ちしております。
Q&A
法務に向いている人はどのような人ですか?

法務に向いている人の特徴とは?未経験・ロー生が法務職で活躍するポイント
法務部で無資格で働ける?

法務部に資格なしで転職する方法|未経験者が知るべき必要スキルと成功事例
法務職の年収はいくらですか?

出典:企業法務担当‐職業詳細|職業情報提供サイト(job tag)https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/446